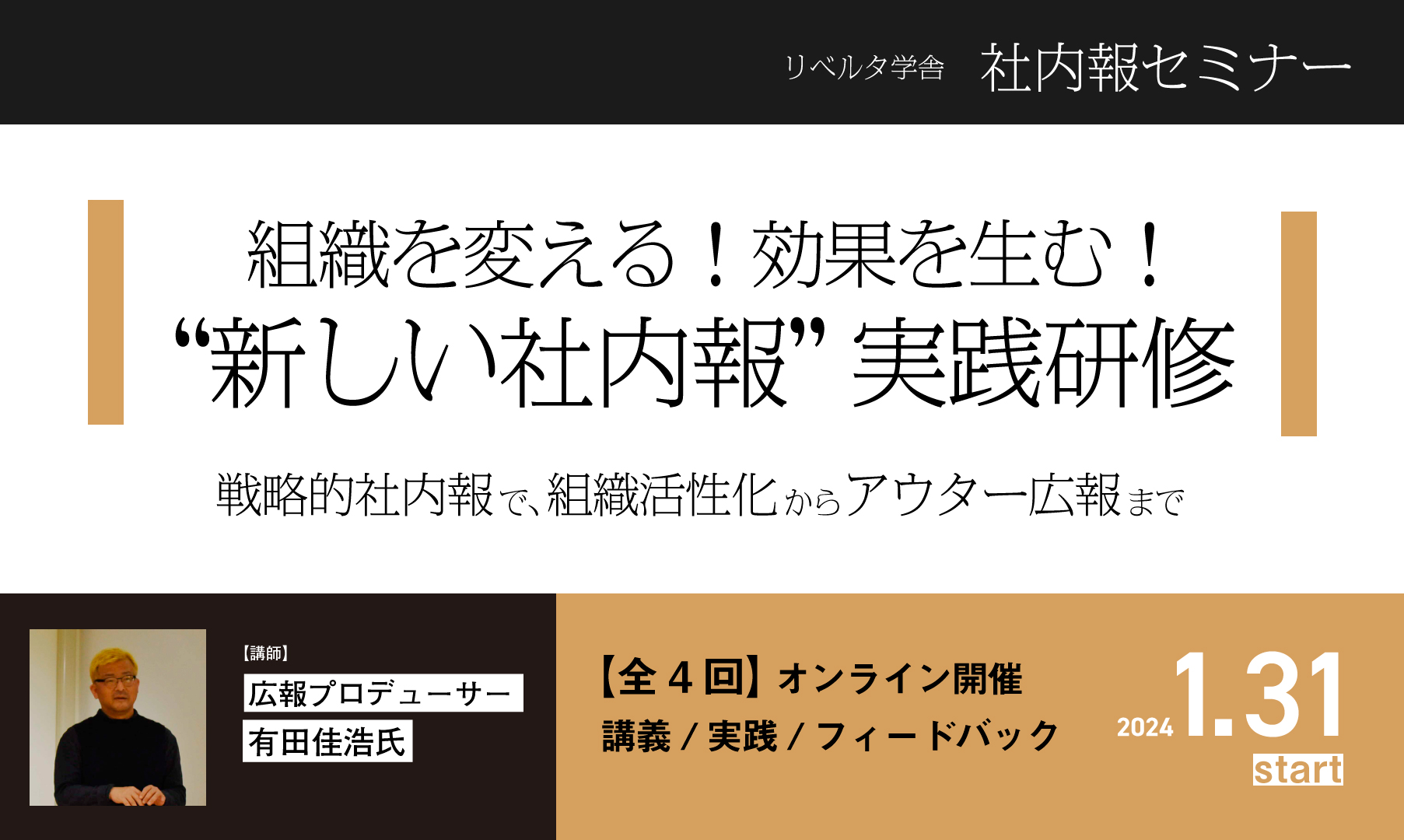2019.11.26
なりわいを考えるシリーズ
おもしろいは、ご自分で。 〜元町映画館 林未来さん〜

文・写真:桂知秋
学生時代に通いつめた、ミニシアターが閉館したと聞き、もうあんな無駄なような、でも愛しい時間を過ごす場所はないのかと、自分の子供たちの青春を憂いていた私が、元町映画館の存在を知ったのは最近のこと。でも、ミニシアターと呼ばれる映画館が存在し続けるのは簡単ではないのだろうという想像はつく。それでも存続しつづける映画館って?
2代目支配人として元町映画館を切り盛りする林未来さんにお話を伺った。
その時にいる人とつくる雰囲気は一回きり
神戸の中心地、元町と西の神戸駅までをつなぐ、大きなアーケード街、元町商店街。古い喫茶店、ドラッグストア、焼き鳥屋、などが並んでいる大きな通りに、チラシのラックが置いてある風景が目に飛び込む。
元町映画館、と大きな看板が出ているけれど、なぜか佇まいはうるさくない。
ガラスのドアを開けると、チラシが積まれた小さなカウンター、次回作と思われるゾンビやドキュメンタリーのポスターが壁一面に貼られ、その奥にはすぐ劇場への入り口が見える。そのぎゅっとつめこまれた狭い空間が、インターネット予約の映画館にいまだ戸惑ってしまう私には、そうそう、これこれ!と胸をざわつかせる。
受付に座っていたスタッフの方に2階へどうぞ、と言われるままに、急な階段を登ると、待ち合いのような小さな部屋が広がっていた。カフェテーブルセットや手編みの椅子カバー、映画の雑誌やチラシが無造作に並べれた棚。そして林さんが忙しそうに壁の飾り付けをしていた。
「明日から始まる映画の展示なんです。ちょうど終わるのでもうちょっとだけ待っててもらえます?」と隣のイベントスペースをインタビュースペースに手早く準備してくださった。
「ばたばたしてて、ごめんなさいね」という林さんの額には汗。「こんな感じでいいんですかねえ?」と屈託なく笑いとばす姿に、一気に場が和む。

「私ね、一生映写技師で生きていく、って思ってたから、支配人にならないか?って言われた時に『やりません』、って断ったんですよ」というくらい、映写技師という仕事が大好きだった林さん。
もともと高校生までは2本立てのアイドル映画やファミリー映画などを観るくらいだったそう。それが、大学時代にたまたま8ミリフィルムのカメラを借りたことから映画に興味を持ち、友人に勧められるがままにミニシアターに通い出し、「今まで観ていた映画とは違う面白さにはまった」。好奇心旺盛な林さんはここで終わらず、さらにボランティアが運営する小さな上映室で映写も教えてもらい、映写技師として働くようになる。
「お客さんが入って、電気を消して、映画が映る瞬間ってのはいっつもドキドキして、それをお客さんの後ろから映しながら見てるっていうのがなんか、何回やっても特別な感じでした。
映画は複製芸術とはいえ、劇場で観る映画はなまものだと思うんですよ。その時にいる人とつくる雰囲気は一回きりだから。同じ映画を頭から終わりまで観れば同じ体験かと言えば、絶対そうじゃなくて」
きっと大学時代に映画と出会ってわくわくしていた時もこんな表情だったんだろうな、と思うような少女のような表情がちらりと見える。
映画館から離れた時期もあったそうだが、「いつかは必ず映画館に戻ると思っていた」通り、元町映画館の設立を知った時、すぐに連絡をした。スタッフみんなでDIYで映画館を作る事からスタートし、映写技師として働くこととなる。

「支配人の一代目が辞める時が、ちょうど映写室もデジタル化が進んでいた頃で、サーバーに本編をいれて上映、映写技師の仕事っていうよりは操作、になっていった時代だったんですよ。まあ結局なにかあったときに対処できないんですよね、やっぱり。映写室でおこったことは映写技師の仕事、みたいなところがあったのに、コンピューター制御になってしまうと、再起動か業者を呼ぶしかないんです。
昔は機械が同僚みたいな感じだったのが、今はピピピとボタンを押して、あとはよろしくお願いしますって感じなんです。もうそれは根本的に仕事がかわりますよね。それを薄々は感じていた時に、『映写室の仕事もかわるよ』って言われて支配人の話を渋々受けました」
おもしろいかおもしろくないか、はその人次第
そうして、映画館の誕生から関わり、元町映画館は今年で10年を迎える。
ー個人的な話ですが、学生時代はミニシアターに通いつめていたのに、最近行かなくなったなあって思ってたんです。
「友達も同じ事言ってて、なんでだろう?って考えたら、Lマガがなくなったからじゃない?っていう話になって。
映画館で観たら面白い、っていうあの頃の熱みたいなものはまだ確実に残ってるんですよね。でも情報誌をぱらぱら読んで、ふいの出会い、みたいなのがなくなったなあって。webだと、欲しい情報にたどりついちゃうから、思いがけない出会いがないんですよね、きっと」
ーそういう意味では、元町映画館さんは商店街にチラシがありますよね。商店街を歩いていたら、あ、次こんな映画するんだ、ってふいに出会える、って面白いなと思いました。
「普通は映画館ってチラシは映画館の中に設置しているから、中に入らないととれないけど、うちは狭かったから、外に出したんです。そしたら商店街っていうのもあるからチラシを見てくれる人が多くて、これは結果的によかったよね、って。けがの功名なんです。結果的には外に出して足を留めて下さる方が多くて。うちは意外と目立たないので」

ーガラス張りで中が見えるのもいいですよね。結構通りすがりでふらっと来られる方いますか?
「さすがにふらっとくるのは常連さんだけです。でも今はほとんどいないですね。そんなふうに映画を観られるのは、年配の方。映画の黄金時代を生きてた方」
林さんによれば、ミニシアターは全国的に若いお客さんはほんとに少なくなったそう。ミニシアターといえば学生が集まる場所、と思っていた私はなんだか浦島太郎のようだ。
ー映画って文化だと思われますか?そもそも文化とはなんだろう?とずっと考えているのですが、、、。
「映画を扱っている以上、映画は文化であり、娯楽であり、どちらもありだと思ってます。でも、文化としての映画は、自分を映す鏡だって私は日頃よく言っているんです。なんていうのかな、その映画を見た時に自分の心がどう動くのか、っていうことで自分を知る、という自分を知るツール。
音楽も本も芸術は全てそうだと思ってます。映画と向き合っているようで、自分と向き合っている。だからね、おもしろい映画っていうのは存在しないんですよ。おもしろい、を与えてくれる映画は存在しなくて、その映画をみたときに自分の心が動いて、そこにおもしろいってことがはじめて生まれるから、おもしろいか、おもしろくないかはその人次第!だからおもしろいは自分の力なんですよ。

作品に相対した時に、自分の心が動いて、自分の中で何かが生まれるものが文化なんじゃないかって私は思ってます。だからいわゆる商業というものとは、はっきり分かれる部分だと思います。(文化としての映画は)消費するものではなく、それを観た時に、自分の中で動いたり生まれたりする」
ー何を感じるか、を自分で。
「そう。なんかね、席に座れば『おもしろい』が与えられるんでしょ?って考えている人が最近は多い気がします。でも99%の人がくそ映画っていってても、自分にとってだけなんか特別、ていうのでも良いと思うし、とにかく、自分がどう思うか。みんながおもしろいって言ったから、よくわからなかったけど、おもしろいんだろうなとかじゃなくって」
今や、映画もレストランもレビューや口コミを確認してから行く、という人も多いのではないだろうか。私自身も心当たりがないわけではない。いつから自分の知らない世界へ一歩踏み出すことを躊躇するようになったのだろう。
「今は多くの人が品質保証というのが欲しいんだろうなと思いますけど、私には星の数を確認してから映画を見る人たちがほんとにわからなくて。この人たちの”おもしろい”は自分の”おもしろい”とイコールなの?って思っちゃうんですよね。
でも絶対そうじゃないし、自分だけのおもしろいをそれぞれ一人一人追求していくべき、なぜならそれが自分の軸になるじゃないですか。自分がどう考えるとか、自分がどういうことに興味があるとか、何が好き、とか。それがなかったらおもしろくないですよね。若い人にそういう力を養ってほしいなと思ってます。とか言い出すと、なんかこれは教育改革だ!とかなるんですけどね」

林さんは大きく笑った。でも表情は切実だ。間髪入れない勢いのある話しぶりに、文化が消えつつある今の状況を日頃から危惧していることがわかる。
「やっぱり芸術に触れないと、人と自分が違うってことが分かったり、人との違いを認めることができないんじゃないでしょうか」
多様性という言葉を昨今よく聞くが、その言葉の大事さは”様々な人がいるということ”ではなくて、”自分とは違う様々な人や考えを認められるかどうか”なんだと思う。でもこれだけ情報が溢れ、なんでも検索で解決できる(と思っている)ような、全てが予定調和の中には、自分の知っている世界以外を想像するすきまなんてない。
「今、情報を遮断されたら、明日なにを着るとか、何を食べるとか、自分の力で選べる人ってどれだけいるんだろうって思うんです。その力が感性だと思うんですよね。感性は筋肉だと私は思っていて、使わないと衰えるし、育てないと鍛えられないから、ずっと心を動かすっていうことをしておかないとだめだと思うんですよ。
感性を育てるには、やっぱり、あの、商業映画は向いてないとははっきり思います。商業映画は1800円分の楽しみを与える作りになってるんですよ。同じところでみんなが泣くように、同じところで笑うように、感情の誘導が親切にされているんです。娯楽なので、自分で感じて、自分で考える、っていうところはわりと意図的に排除されてるんです。それが娯楽ですからね」
「でも商業映画とそうでない映画は違うものだとは思うし、自分の頭を使わないといけないとかそういうしんどさはもちろんあるとしても、やっぱりそういう映画の魅力を伝えたいです。と思いつつ、なかなか伝わらないですけどね」
余白を残す映画館でありたい。
インタビューのあいまあいまに、どうしたらもっと魅力が伝わるんだろう?どういう発信をしたらいいんだろう?と悩む姿を見せる林さん。映画は文化か商売か?と問われることも多いとおっしゃっていたその質問を改めて尋ねてみた。

「映画は文化だと思っているし、商売のつもりでやってたら成り立っているのか成り立ってないのかよくわからない。うちも結果的にほぼ非営利みたいになってます。でも私達は文化と思っているから、それを絶やさない為に、守っていこう、っていう想いでやってるんですけどね。でもそれが大きな会社が経営しているシネコンと映画館という名前だけでひとくくりにされて、映画は商売だから、って言われるのは困っちゃいます」
「安いお給料でもいいんですけどね」と林さん。でもそれでは若いスタッフは将来が不安で辞めてしまうそうで、これからの世代が育たない、つまり映画文化自体が廃れていくことにつながることは心配している。
ーでは、これからの元町映画館をどうしたい、というのはありますか?
「自分たちが『うちはこういう映画館だから』って外に向けての発信っていうのはあんまりしたくなくて、色んな人に関わってほしいんです。色んな人が色んな面白さを作って行く場所だといいなとずっと思っていて。私も二代目ですけど、つぎ三代目、四代目になってどんどん形を変えながらも、とにかく続いて欲しいなと願っています」
「今では、外部の人もここをこうしたら面白いんじゃないかとか、例えばこの部屋の面白い使い方を考えたとか、そうやって関わって下さる人が増えてきました。みんなで面白い場所を作り上げるのが私的には理想だと思ってます。今なかなか忙しくて、余裕がない事も多いんですけどね笑」

神戸に来て10年。観察してきて気がついたのは面白い人が点在している、ということだそう。だから林さんは元町映画館という場所で繋げていきたい、と企んでいるそうだ。映画館という場所が自由な存在に思えてくる。
「ミニシアターっていうのは、例えばルネッサンスの芸術とか日本映画でいえば溝口(健二)とか小津(安二郎)みたいに固まった形のあるものではないと思っていて、まだまだ有機的なほうがおもしろいなって思っています。その時代とか街とか、人とかによって形を変えていきつつ、つねにおもしろい場所である、っていうのが、まあ概念上では理想です。だからまだその形を固定してしまうには早いし、もったいない」
ー余白を残しながらやっていく、みたいな。
「そうですね。で、やっぱり全国でロードショーとかしない若手の監督の作品の上映の機会をつくれるのもミニシアターだから、新しい才能っていうのもやっぱり時代によってそれなりに色があったりもするので。その都度その都度、新しい才能も紹介していきつつ。だからなんか、ただの箱だと、思います」

上映する映画や芸術に対してたくさんの想いも、やってきた積み重ねもきっとあるけれど、うちはこんな存在だよ!と押し付けはしない。この映画館に来れば、こんな映画が揃ってるよ、感性が育つよ、とは言わない。箱は用意する、あとは関わる人たち次第、なんだと。それはまるで林さんが思う「文化としての映画」のように。
色んな人がどんどん関われるようなすきまがあれば、それぞれが自分ごととして捉え、関われる。映画が自分と向き合い、自分軸をつくる存在だと思っているように、映画館というものも、関わる人の自分軸をつくり、感性を育てることにつながる。そう思ってらっしゃるのではないだろうか。
簡単に聞こえるが、それは一歩間違えれば人任せの放棄になる。でも違う。文化としての覚悟。そう感じた。そしてそれがこの映画館の佇まいにつながっているのかもしれない。
取材を終えて。

帰る間際に林さんがだしぬけに放った一言が、心の奥底に小さな石のように転がっていた。
「映画も好き、映画館も好き、でも自分の好きはわりとどうでもいいんですよ。自分の好きを他人と共有しなくてもいいタイプなんで。それより、私は働く事が好きなんです、きっと」
「映画の仕事を離れていた30代のころに、結構色んな仕事をやってたんですけどね。仕事はどんな仕事でも真面目にやったら楽しいんですよ。手を抜いてだるいな、ってやってたらなんでもだるいんですけど。仕事はなんでもおもしろいんです」
これまでの内容を翻すかのような言葉。でも”働く”という根源的な、とても大事な何かに触れているのでは?という気がして、ぐるぐる頭を駆け巡った。
あ。「映画の”面白い”はその人次第」という林さんの言葉が頭の中でプレイバックした。まさに仕事を自分ごととして捉えて、向き合っているからこその言葉じゃないか。林さんは仕事に”面白い”を与えてもらおうなんて、きっと1ミリも思ってないのだ。
そう、”好きを仕事にする”なんて、簡単に吹き飛ばされそうな甘いささやきに思えるくらい、林さんの言葉には、あたたかで、血の通った、しなやかな軸があった。それはきっと、林さんご自身が感性を文化に育まれた、何よりの証拠なんだ。
映画という文化が林さんを育み、そんな林さんだからこそ地域の人に、自分という一線を超えてみたら?と場所を開く。大袈裟に言えば、そういうことなのかもしれない。
「え、そんなことないですよ、私、何にも考えてないですから」”映画の仕事じゃなくても楽しい。” ”シネフィルでもない。” 映画館や文化へのほとばしる想いを照れ隠すように、そういう言葉をちらりと見せる林さんのことだから、そうおっしゃるかもしれないな、とここまで書いてふと思う。
でも。もしそうだとしても、その言葉のすきまがあったからこそ、私は想像し、考えを巡らせ、自分と向き合いすらしちゃったんですよ、林さん。だからきっと林さんなら許してくれるはず、と密かに信じることにしよう。だって私の感性はもう心地よい筋肉痛だもの。
元町映画館

桂知秋CHIAKI KATSURA