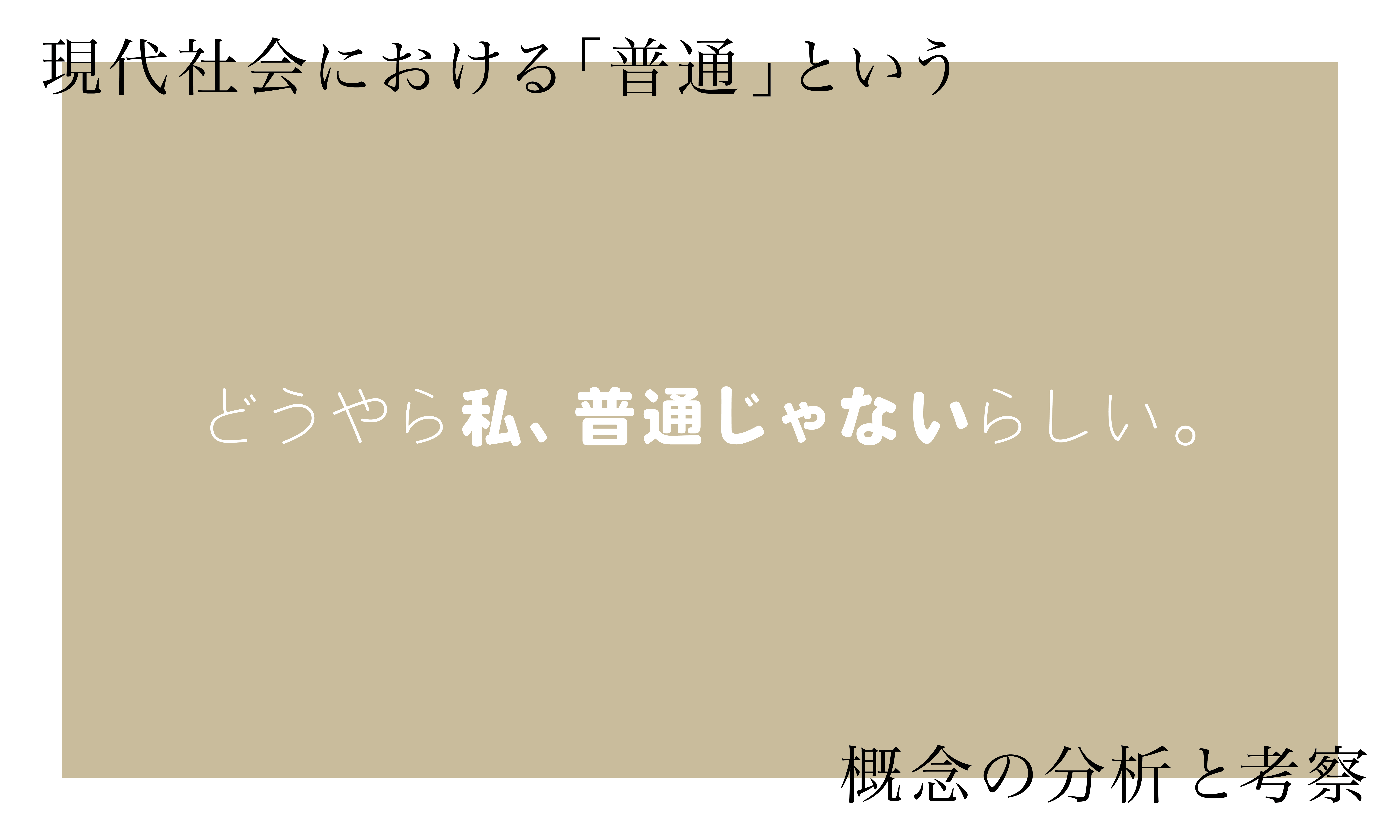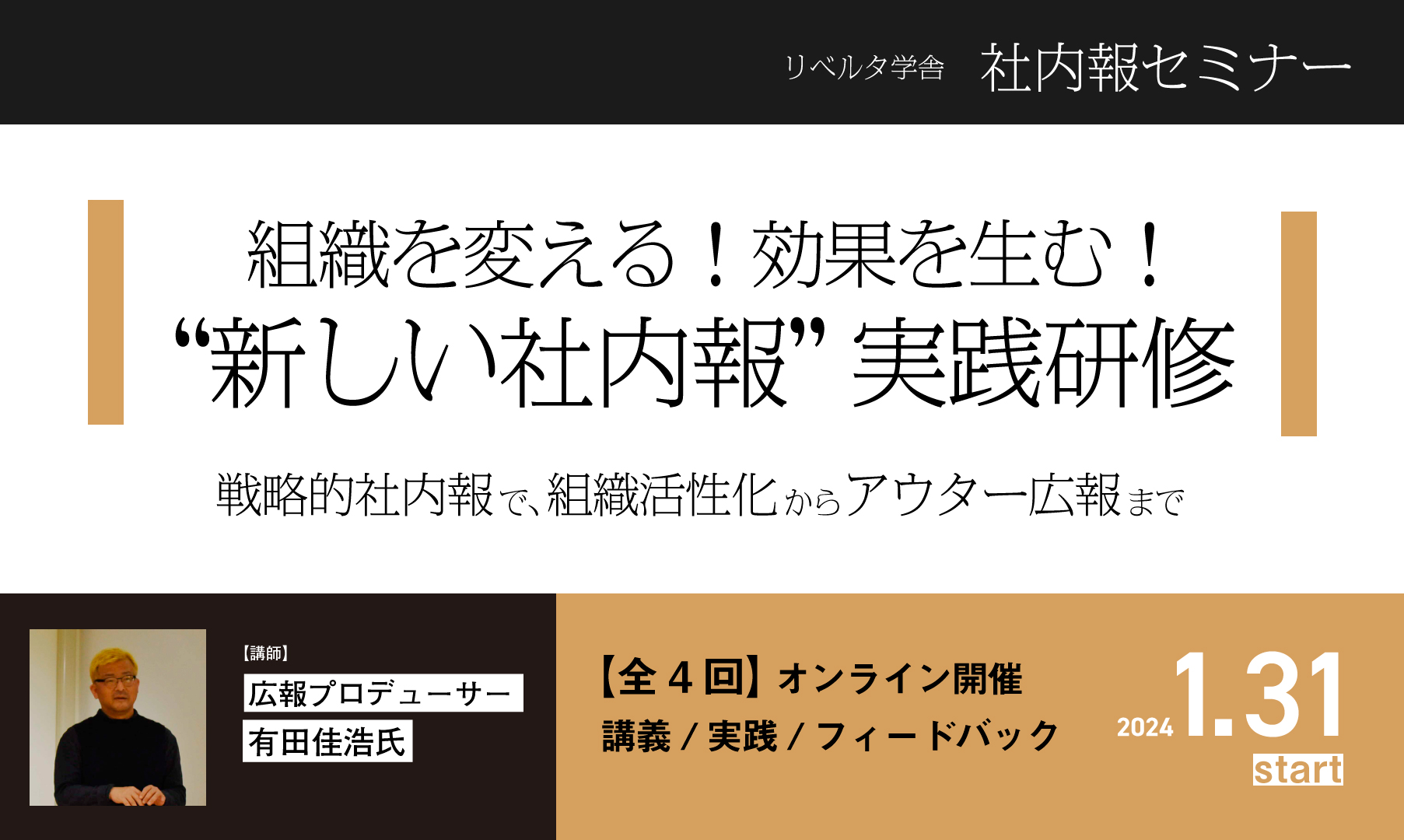2023.09.28
なりわいを考えるシリーズ
変化に抗っている時間が、いちばん人間らしいのかもしれない ~レストラン「anonyme」シェフ 加古拓央さん

文・写真:松本理恵
中学生になった長男の声が少し低くなった気がする。そんな息子の“変化”には、成長の喜びもあるけれど、“幼さ”との別れのような寂しさ、まもなく訪れる思春期への不安も。私はこういう“変化”が苦手だ。受け入れるのにいつも気持ちが追いつかずじたばたしてしまう。「変わること」をどう捉えれば、焦らず向き合えるのだろうか。 神戸にあるフレンチレストラン「anonyme」のシェフ、加古拓央さん。26歳の時に「レストロ エスパス」を開店、その後、店名や場所を2度も変え、50歳なった今も変化し続けながら、カジュアルにフランス料理を楽しめるお店を営む。加古さんにとって「変わる」ってどういうことなんだろう。
お店の定休日にanonymeを訪ね、加古さんに話を伺った。
「理解してもらう」ことは、幻想に近い
誰もいない静かな店内のテーブル席で、加古さんと向かい合って座った。20代の頃、エスパスに初めて伺って、加古さんとは他にもいろんなご縁があるのだけれど、ゆっくりと話をするのは今日が初めて。少し緊張する。
唐突だと思いつつ、最近ずっと考えていることを尋ねてみた。それは「料理で“母の愛”は伝わるのか」ということ。毎朝、私が作った弁当を無言で受け取り、夕方、空の弁当箱を面倒くさそうに台所に出してくる長男。そもそも料理で何かを伝えようなんて、やっぱり無謀なことなのだろうか。

加古さんは少し考えて「僕としては、今のお話のように“何か”を伝えたいとは思っている」と言ってから、こう続けた。
「ただ、その“何か”が自分でもわかってないから、多分、伝わるわけがないですよね。そもそも理解されていると思うのが幻想だし、たまたま理解に出会うことがあれば、そんな光栄なことはないけれど。家族であれ、お客さんであれ『こんなことをすれば、喜んでくれるはず』って思っていること自体、実は傲慢なことなのかもしれない」
弁当に長男の好きな唐揚げや春巻きを入れても、何も伝わった感じがしないのは、そもそも自分のスタンスが違っている気がする。だとしたら、どんな気持ちで料理を作ればいいのだろう。
「伝わるわけがないと思っているから、僕は『自己満足』で料理を出していることになる。でも受け取り方も『十人十色』だと思う。だからお客さんが喜んでくれたらうれしいけど、自分の仕事ができていなかったら、うれしさには繋がらない」
勝手な想像で、料理人はお客さんひとりひとりの味覚に向き合うものだと思っていた。自分がいいと思う料理を作り、どう受け取るかは相手に委ねる。そう考えると改めて料理は対話であり、表現なんだと思う。
「昔の画家がどんな思いで絵を描いたか、後年の研究者が言っていたとしても、本人はそもそも『何かを感じてもらいたい』なんて思ってなかったかもしれない。作ることが“衝動的なこと”に近いのかなと思うと、僕の場合、たまたまその部分を商売、なりわいとして生きて来られたのはラッキーだったなとは思う」
でも、表現でありながら、お店で出す料理は「作品」ではないという。料理を出した瞬間にお客さんの会話が始まって、食べるベストのタイミングを逃すこともある。そういう意味では、自分の納得する料理を出したいけど、どこかで諦めているという加古さん。大切なのはあくまで店全体のバランスや空気感であって「初デートで来た若いカップルが緊張しながら、でも最後は楽しく過ごしてくれたらうれしいですよね」と言ってにっこりした。
できれば変わらずに、変わりたい
「商売である店の運営と料理人としての自我は別々だと思う」という加古さん。これまで1人で仕切るカウンターメインのお店の時もあれば、スタッフのいる大きな厨房があってテーブル席メインのお店の時も。料理もアラカルト中心だったり、お任せコースのみだったり。お店の形に伴うお客さんとの距離感も、その時々で変えてきた。

―私は“変化”への耐性がめちゃ弱いんですが、加古さんは強い方なんですか。
「僕もそんなに強くない。できれば変わらずに変わるというか。単純に飽き性なのはあるが、変化を好んでいるわけではない。でも特にフランス料理は80~90年代以降、3年とか5年、もっと言えば1年のスパンでも劇的に流行が変わっていく。そこに乗らないことには、生き残っていけない。だから変わらざるを得ないし、逆に変わることに踏み出せたから、今まで店を続けて来られたのかなと」
―世の中には信じられないほどフットワークが軽い人もいますが、そうではないと。
「2010年にanonymeに移るまでは、変わることに対して苦労はしてなかったというか、もっとフットワークが軽かった気はする。でも今50歳の人間に新しい道が他者から用意されるわけではないから、自分で行くしかないし、かつ守るものもあるという時に、踏み出すのは怖いし慎重にならざるを得ない。一方で、タイミングを見失う怖さもある」
変わりたい、ではなく変わらざるを得ない。でもそうさせているのは、料理の世界をめぐる流行や多様化、グローバル化といった情勢だけではない。
「例えば、ビジネスとしてパッケージ化されたものが「世の中の成功」なんだとしたら、そこは僕たち職人が行く場所ではないというか、面白くなくなる。自分の仕事がルールになるほど楽しくないだろうし、成功の形ってそんなに続くものじゃない。毎回違うお客さんが来て、いろんな食材が季節で変わっていくわけだから、料理人として自由に向き合えることの方が、僕としては楽しい」
―つまり、自分が面白がって仕事を続けていくためにも、変わらざるを得ないという。
「そう。変わらざるを得ないし、変わっていくというのもある。20代の時と同じ音楽を聴いているわけじゃないし、同じ作家の本を読んでいるわけじゃない。変わっていないように見える人たちも、実際ミクロではめちゃくちゃ変わってきているだろうし、変わらない人はいないと思います」
“自分が変わっていく”という感覚について心当たりがあった。かつて組織で仕事をしていた私は「働く母」になってもヒールのある靴で出勤することにこだわった。でも帰りは子どもの迎えがあるからいつも走っていて、足は痛いしヒールの先がすぐにすり減る。それが何年か続いたのだが、ある日突然スニーカーでもいいかなと思った。実際にスニーカーを履くと驚くほど快適で、心がちょっと優しくなれた気がした。違うかもしれないと思いつつ、そんな話をすると加古さんはこう言った。
「人には、それぞれ美学があるから、未だに無理してヒール履いている人に『スニーカーのが楽やのに』って言うのも違うし、スニーカーだからといって『何か捨てちゃったな』って言われるのも違う。でもヒールの靴の時、スニーカーになった時、どちらも生きていく上で必要な時間だし、意地張ってヒールの靴を履いているタイミングが、実は一番人間らしい時間なのかもしれない」
変化といえば、成長とかステップアップとか、変わった後に「こんなに良くなった」という文脈で語られることも多い。でも変わる前、変化に抗っていた苦しい時間を「人間らしい」と表現された時、カツカツとヒールの先をすり減らして走っていた自分の姿が、急に鮮やかに輝きだしたように思えて、ちょっと泣きそうになった。
便利なこと、楽であることを否定しないけれど
加古さんは、自らを「悩むタイプ」と公言しているけれど、話をすればするほど、料理人としての自分も、これまでの自身の変遷もすべて肯定して、自分の軸で歩んできている人だと感じる。それでもなお、悩み続けるのはなぜだろう。
「お店としてお金をいただく以上は、何かしらの制約は当然ある中で、失いたくない『自分らしさ』もある。それに納得とか完璧とか上を見れば見るほどないし、でも折り合いはつけていくしかないですよね」
―自分の納得に折り合いをつける、ですか。
「もうそれは『どう引退するか』みたいなことになると思う。上がり続けるのはめちゃくちゃかっこいいんだけど、かっこいいかどうかも人それぞれ。スポーツのようにはっきり引退のある世界では、サッカーの三浦知良選手みたいな“やり切る美しさ”もあって憧れますよね。でも料理人という引退のない仕事を続けたいと思う以上、やり切ることはできないし、ソフトランディングの仕方を探りつつ、最後に『もうちょっといい料理を作りたかった』って思うくらいが理想というか。たぶん納得したらあかん気がします」
―私、書くことを仕事にして初めて「あなたのいいところは悩むこと」って言われて、「えっ?」ってなっていたんですけど、悪いことじゃないという気がしてきました。
「そうなんですよ。自分の仕事に関しては、悩んだり迷ったりする人間らしさみたいなことがなければ楽しくないなと思いますね」
悩んでいる時間はしんどい。時には沼の底にいるような暗い気持ちになることもある。でもうんうんと自分の中で反芻することで、思いもよらなかったことに気づき、頭の中にパッと明かりが差すと面白くなってくる。

「お店にしても食べるものにしても、全ての選択に関して、スマホを開けば『おすすめ』がどんどん表示されて、みんな考えて選んだり、悩んで決めたりすることが苦手になっている気がする。もちろん便利なことを否定はしないけど、AIに選んでもらったら考える余裕もないし、気づくこともないから面白くない。辞書で調べた時の前後の言葉や、本屋さんで買う本を迷っていた棚に思わぬ出会いがあって、心が動いたりする。そういう“人間臭さ”を残してかないとダメ、というよりは、僕は多分そこでしか生き残っていけないと思う」
―仕事でタブロイド紙などの紙媒体に関わることがありますが、新聞もそう、気になった記事から自由に読めて、その隣の記事に新たな出会いがあることも。WEBの時代でも存在する意味はあると思っています。
「そうですね。紙の媒体は残ってほしいし、意味のあるものはこの先も何らかの形で残っていくと思っています。でもどんな媒体であれ、多くの人に届けることが正解ではなくなってきましたよね。CDセールス100万枚とか、その設定自体が成り立たないじゃないですか。だから食べものを作る上でも広い範囲の人にわかってもらわないとダメっていうのも、もういらないような気がします。
あとはコミュニケーションも。ごはん屋さんでも会話のない店は楽だし、楽な方へ流れるというか、どんどん面倒くさくなるものだから減っていくだろうけど、無くなりはしないと思う」
15年以上も前に、加古さんのお店で「焼きナスのブリュレ」をいただいた時のこと。香りがすごく印象的で、帰りに感想を伝えると、加古さんは「ありがとうございます」と笑顔で言ったあと、「でもそれは、僕の中ではもう飽きてきているんですよね」と不意に真顔になったことを覚えている。「悩んでいることを簡単にお客さんに言っちゃうからダメなんでしょうね」と加古さんは笑うが、この時の会話があったから、私は今こうして加古さんと話をしている。
居心地がいいとか、波長が合うとか
anonymeは、神戸の中心地から少し離れた駅で降りて、徒歩3分ほどの静かな路地裏にある。「最初のエスパスもそうですけど、人がおらへんところも、自分で空気が作れるから楽しい」という加古さん。通りすがりというよりは、わざわざ目的を持ってアクセスしてもらうお店にしている。

「僕は、お客さんとの距離感って『友情関係みたいなもの』と思っているんです。友だちとクラスが一緒になったり離れたりするなかで、別に嫌いなったわけじゃないけど遊ばなくなったり。それでもずっとつき合いが続くのは奇跡やと。
店も同じで、何かで知って来てくださって、喜んでもらえたらうれしいんですけど、それが続くわけがないと思っているんですね。不味かったわけでもない、気分を害したわけでもないとしても、通い続けることがまれやと思うんです。新しい店にも流れていくし、その方にもいろんなことがあって、それでも通ってくださるお客さんは本当に奇跡でありがたいですよね」
確かに、人づきあいの中でつながる感覚や続く理由を説明するのは難しい。一緒にいる時間は長いのに馴染めない人もいれば、取材で30分ほど話をしただけで驚くほど互いの距離を近くに感じる人もいる。学生時代からの友だちに今でも会いたくなるのはなぜだろう。
「友だちの好きなところを『ここ』とか言えたら、僕はウソやと思う(笑)。でもあえて言うなら、居心地がいいとか、波長が合うとか、そういうことなのかもしれないけど、お店に来てもらうお客さんに対しても、結局そういうことだと思う。だから目の前の仕事のことはすごく考えるけど、それ以外はあまり考えない」
加古さんは「お客さんの方を向いてない」という。全ては目の前のお皿。でも向き合い続けるのは容易なことではない。常に変化と対峙しなければいけないし、表現であるはずの料理は、時に「根拠のない他者の評価」の対象にもなる。「料理は好きだけど、やっぱり仕事にしちゃうとしんどいですよね」という加古さんにとって、続けていく力になっているものは何だろう。
「何度も来てくれるお客さんと知り合ってお話をするという、奇跡みたいに最高な瞬間が時々あるんですよね。たぶん僕が学生時代に想定していた『普通の人生』では話をしないであろう人たちが、丁寧に知らない世界を教えてくれて、僕は料理人として腕組みしながら話を聞ける。それが原動力かな」
お客さんとの会話から生まれる奇跡的な瞬間を、加古さんは「ご褒美」だと言った。それはサッカー選手がゴールを決める時のように、積み上げてきたことの「目に見える成果」とは違う。思いもよらないところから不意に舞い降りてくるからこそ「ご褒美」なのだと思う。
とある土曜日の午後6時、anonymeに食事に行った。一番乗りでお店に入って席につくと、後から予約のお客さんが次々に入ってきた。みんなの表情にワクワク感があふれていて、この華やいだ店内の空気感がどこかに似ていると思ったら、出発前の空港のロビーだった。旅の楽しみ方が自分次第であるように、お客さんに料理の楽しみ方が自由に委ねられているお店で、この空気感が生まれるのは必然なのかもしれない。
取材を終えて
日々生活をするなかで、自分の力ではどうにもならないことがある。それは、悪いことだけではなく、最後に加古さんが言った「ご褒美」もそう。大切なのは、どうにもならないことを考え続けるよりも「自分ができること」に向き合うことではないだろうか。
そう考えると、変化に対しても同じかもしれない。焦ってじたばたしてしまうのは、自分の力が及ばないところに気持ちが囚われているから。例えば、息子に弁当で「母の愛」を伝えようとするとか。私ができるのは、自分がいいと思うおかずを詰めることだけだ。今、自分の手の中でできることは何か、そう考えるだけで、変化への焦りや不安の波が少し静かになっていく気がする。
とはいっても、変化の中では感情が揺さぶられることだってたくさんある。結果、バカだなぁと思うようなことをしてしまうかもしれない。でもきっと悪いことではない。それが加古さんのいう「人間らしさ」だと思うから。
anonyme(アノ二ム)

なりわいカンパニーuser